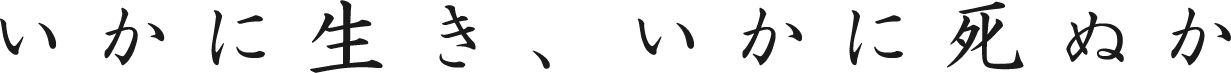
圓應寺 住職法話
住職法話 第153回
緩和ケア医療に学ぶ生と死
【生と死の考察】164~170
「少子化・人口減少が及ぼす生活・医療・介護への影響」
前回までのこの項では、友人と檀家さんの中で印象に残る方の死についてて考えました。今回は、一時中断して少子化・人口減少が及ぼす生活・医療・介護への影響について考えます。
Ⅱ-164 出生数80万人割れ

厚労省2023年2月28日発表の「22年の人口動態統計」によると、22年に生まれた子どもの数(外国人を含む)は799,728人で、統計のある1899年以降、初めて80万人を割り込みました。
さらに、厚労省23年6月2日発表の「2022年の人口動態統計」によりますと、日本人の子ども(出生数)は、出生数も合計特殊出生率(一人の女性が生涯に生む子供の数を推定した人数)も過去最低となりました。これによりますと生まれた赤ちゃんは77万747人で統計を取り始めた1899年以降で最少となり、この統計でも初めて80万人台を割り込んでしまいました。合計特殊出生率は1.26に落ち込み、データーのある1947年以降20005年と並んで過去最低となったのです。加えて出生数の減少ペースは速まり、2021年は前年比3.5%の減でしたが、昨年は前年比5%も減少となったのです。
1982(昭和57)年の出生数は151.5万人だったのですが40年間で半減の状態に落ち込んでしまったのです。しかもこの現象は年々加速しているのです。2017年に国立社会保障・人口問題研究所が出した国内日本人の出生数が76万人台になるのは2034年と予想していたのでしたが・・・・。進む少子化について厚労省は「若者の経済的不安定さ、コロナ下での妊娠や出産、育児への不安が影響した可能性」があるとみています。
Ⅱ-165 出生数の歴史

2023年3月1日付朝日新聞は「早まる少子化 日本危機」と題して、出生数の歴史とその影響について述べました。端的で良くまとまった内容ですので、この記事を基に先ず出生数の歴史を振り返ります。出生数は「団塊の世代」が生まれた第一次ベビーブームと言われた1949(昭和24)年、戦後最多の269.6万人。第二次ベビーブームの71(昭和46)~74年では毎年200万人を越えたものの、その後は減少して現在に至っています。このような急激の少子化について「経済や社会の基盤が大きく揺らいでくる危機」(当時の加藤厚労大臣)と言われ、「年金をはじめとした社会保障制度、労働力を基盤とした経済活動など゜幅広い分野に影を落とす」と述べています。
Ⅱ-166 少子化の具体的影響 ①

具体的には、①労働力人口が戦後増加傾向が続いてきたものの、今後については第一生命経済研究所・星野卓也氏の「20年代半ばをピークに労働力人口も減少に転じ、19年に6900万人だったのが40年に6200万人台まで落ち込むと予測」との見解を紹介しています。②さらに同氏の見解「実質国内総生産(GDP)成長率は労働力人口の減少による押し下げ効果も あって、30年代には0%台前半に落ち込み、40年代にはマイナス成長に陥る」との予測を紹介。③年金については、「19年に国が公表した年金額の将来見通しによると、高い経済成長を前提にしたケースでも47年度の年金水準は実質2割低下すると見込まれていた。だが、将来人口推計の実際は、さらに速いスピードで少子化が進む。将来の年金水準がさらに低下する恐れがある」と、年金の危惧を訴え。④「高齢者人口がほぼピークを迎える40年度には、約280万人の介護職員が必要と見込まれるが、19年度時点で担い手は約211万人。約69万人を新たに確保しなければならない計算だが、少子化で働き手不足が一層拡大する恐れがある」ことを紹介。介護を受けたくとも受けられない事態が心配されます。在宅での日常の介護サービスと施設入所による介護サービスの双方に深刻な影響が心配されるのです。
Ⅱ-167 少子化の具体的影響 ②

このような心配は、現時点では表面化していませんが、介護にとどまらず看護にまで影響するのではないかと危惧されます。人口減少で病床数が削減されている中ですが、看護者不足による病床削減という事態になりかねないことを危惧しています。新型コロナ下での医療現場の大変なご苦労が報じられた中、その過酷さの影響もあってか、各医療機関にあって看護定員割れの実態を見聞きするのです。少子化・人口減少の中、多くの職場で人手不足が叫ばれています。命に関わる介護職と看護を中心とした医療職の労働対価を改めて見直す政策が求められのではないでしょうか。
Ⅱ-168 「出産・子育て『500万円の壁』」

さらに同紙は、少子化対策への提言として「政権が掲げる『異次元の少子化対策』をめぐって~中略~議論の中心となっているのは、児童手当の増額や保育園の質の向上だ。こうした親への支援だけでなく、置き去りにされている課題もある。その一つが若いカップルに立ちふさがる『500万円の壁』だ。」として、22年2月に内閣府が公表した「日本経済2021ー22」の内容を次のように紹介しています。「世帯所得が500万円未満の世帯では子どもを持つという選択が難しくなっていることがうかがえる」と。さらに同リポートの詳細を次のように紹介しています。「世帯主が25~34歳のうち、子どもがいる夫婦世帯の14年と19年のデータを比較、その結果、世帯所得が『500万円未満』の層は、26.9%(14年)から15.9%(19 年)へと11ポイント低下していた。この数字の低下が意味するのは、世帯所得が500万円に届かない夫婦が、子どもを持つという選択を出来なかった可能性だ」と指摘。その反対に500万円を超える層では「4.6%(14年)から7.1%(19年)へと増加」しており、内閣府は「少子化の対応に当たっては、結婚や子育てを控える25~34歳の層世帯所得の増加が重要」と分析していることを紹介しました。
Ⅱ-169 奨学金の返済問題

続けて同紙は「『奨学金』の返済負担は今の20代、30代から結婚と出産を遠ざける要因の一つ」として、一人の国立大卒者の例を上げ、貸与型の奨学金252万円の返済に、月々1万4千円。これが38歳まで続き、「結婚したら借金が倍増する。結婚するぞ!と前向きにはなれない」と。さらに同氏の「高齢化で社会保険料が上がり続ける時代を生きる世代なので子どもを産むだけでなく大切に育てていけるのか、自信を持てない。将来の不安を和らげるため、教育の完全無償化が必要」との声を紹介しました。
Ⅱ-170 少子化への根本的対策

以上のように少子化の根本的対応は、目先の手当や保育所対策だけではなく、若者が結婚できしかも子どもをもうけられる生活水準そのものへの対策が必要なのです。そのためには、教育の無償化に向けた対策と共に、非正規労働を出来るだけ無くし、正規労働が当たり前の社会的対応が必要なのです。今こそ生活基盤そのものへの根本的対策が求められているのです。
最後に同紙は、子どもの学習支援をする認定NPO法人キッズドアの渡辺由美子理事長の見解を次の通り紹介しました。
「産みたくても産めない若年層への投資を今すぐ実行すべきだ。国際的に日本の経済的地位が低下し、高齢化で社会保険料も上がって給料の手取額は減るばかり。奨学金返済が月数万円あって若者は将来の結婚も出産も諦めてしまう。~中略~結婚や出産した場合の奨学金の返済免除、大学や専門学校などの完全無償化、少なくとも無償化の対象を中間層まで広げるといった対策が必要だ」と。
文科省の「子供の学習費調査」によると、小学校から高校まで公立校に通ってもトータルして527万円。国立大学で入学金と授業料が242万円~291万円。小学校からの合計では800万円を超えることに。私立の場合は、優に1000万円を超えることになってしまうのです。
最近の日本は「国力が落ちた」と言われるようになりました。その指標の一つに実質賃金の低下が上げられます。厚労省「毎月勤労統計調査」によると、1996(平成8)年から2022(令和4)年の26年間に、労働者一人当たり年間64万円も減少しているのです。このように日本全体として厳しい状況下にある中、少子化への根本対策として打ち出された「異次元の少子化対策」が実のあるものになることを期待し、必要な時に必要な医療そして介護を受けられる社会であること。同時に年金をはじめとする社会保障水準が維持され、安心した生活が出来るようになることを期待してやみません。


