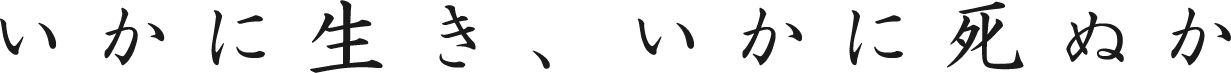
圓應寺 住職法話
住職法話 第118回
緩和ケア医療に学ぶ生と死
【生と死の考察】122-127
「『終末期の療養生活に関する実態調査結果』について考える」
明けましておめでとうございます。皆様と共に新年を迎えることが出来たことに感謝しております。 昨年は新型コロナ禍で自粛・自制・制約そして生活破綻等々、厳しい生活が強いられた一年でした。影響は各界に及んでいますが、葬儀・法事のあり方にまで・・・。
私の寺には最上三十三観音霊場第四番「圓應寺観音」があります。昨年は12年ぶりの「子年(ねどし)最上観音札所連合御開帳」が行われる予定でしたが、オリンピック・パラリンピックと同様に、御開帳は一年延期となり、今年5月~半年間実施することになりました。現時点では実施する予定で準備を進めており、無事開催できることを心から願っているところです。
さて、前回のこの項では、檀家さんの中で印象に残る方の死について考え、その4回目について述べましたが、今回はこの続きを一時中断し、ガンで亡くなった方の遺族に対して行われた「終末期の療養生活に関する実態調査」結果が発表されました。その内容は多く課題と問題を提起していると考え、特に、次に示す①「亡くなるまでの一ヶ月間に患者が痛みを感じた(人が)40.4%」に絞り、急遽この調査結果について考えることにします。

Ⅱ-122 国立がん研究センターによる遺族に対する「終末期の療養生活に関する実態調査」(2020年10月30日発表)結果について
その調査結果の概要は次の通りです。
① 亡くなるまでの一ヶ月間に患者が痛みを感じた … 40.4%
② 患者がつらい気持ちを抱えていた…42.3%
③ 人生の最後に求める医療や療養場所について患者と医師間で相談できた…36.5%
④ 人生の最後に求める医療や療養場所について患者と家族間で相談できた…42.4%
⑤ 介護したことで家族の負担が大きかった…40.9%
⑥ 遺族が長く嘆き悲しんでいた…30.1%
⑦ 遺族にうつ症状があった…19.4%

Ⅱ-123 実態調査結果について考える ①
調査結果で1番目を引くのは、①の「ガンで亡くなるまでの一ヶ月間に『痛みを感じた』患者さんは40.4%」という高い数字です。近年、身体的精神的痛みを緩和するための専門病棟である「緩和ケア病棟」やホスピスが全国的に創られ、全国の施設と病床数は1990(平成2)年時はたった5カ所で120床でしたが、2019(令和1)年には431カ所、8802床と飛躍的に増加し、珍しいものではなくなりました。
加えて、専門の病棟だけで緩和医療をするのではなく、その経験を院内の他の病棟や他の病院、そして地域を含む医療界全般に広げた「緩和医療」もますます盛んになっており、経験を積んだ医師や看護師を中心に「緩和ケア医療チーム」を組織して活躍するようになってきています。したがって今や緩和医療は当然ながら緩和ケア病棟専門の医療ではなくなっているのです。
しかしながら亡くなるまでの一ヶ月間に4割の方が痛みを感じていたという調査結果です。痛みについてはその個人差があること、そしてその程度など様々な容体があると思いますが、それにしても高い数字と言わなければなりません。

Ⅱ-124 実態調査結果について考える ②
この数字の高さを見ますと緩和医療の実態は「まだまだ」との実感です。この数字は、ガンによる身体的痛みを指していると思いますが、身体的痛みの緩和は患者さんの精神的痛みをも和らげ、安定感をもたらします。そのことによって患者さんのQOL(生活の質)の向上をもたらすいわば原点・基本なのです。これは、多くの医療関係者にとっては常識となっているはずなのですが‥。
身体的痛み(苦痛)はガンによる直接的な痛み(がん性疼痛)のみではありません。手術後の傷の痛み、放射線や化学療法などでの副作用としての痛み、長時間寝たきりによる褥瘡(床ずれ)の痛み、その他吐き気や便秘等々です。この他当然ですが、人としての精神的痛み(経済的、職業的、霊的等々)も伴いますが、このことについては今回は省略します。
さて、調査結果を詳しく見ると、痛みが少なかったのは、緩和ケア病棟の患者さん → 介護施設や老人ホーム → 自宅 → 病院の順でした。ここで驚きは、24時間医療スタッフがいる病院が最下位ということです。在宅よりも施設よりも痛みを持った患者さんが多かったのです。近年、在宅緩和医療が進んできていると言われていますが、病院の最下位には驚きます。このことは医療の本丸とも言うべき病院に於いての緩和医療がまだまだであることを示しています。

Ⅱ-125 実態調査結果について考える ③
多くのガン患者さんの望みは「痛みの緩和」です。最近、「エンディングノート」、国による「アドバンスケアープラニング(ACP 人生会議)」の作成等、いわば「終活」に関する推奨が目につくようになりました。平均寿命が男子81歳、女子87歳となった日本社会、「人生100年」と声だかに言われる時代になりました。この「人生会議」等については後日、別項で詳しく触れる予定ですが、要は定年退職後の人生をどのように生きるのか。しかし寿命はいくら延びても必ず「死」はやって来る、その準備をどのように進めるか。そして人生の最後の段階にどのような医療を期待するのか等々について家族、場合によっては医療者を含めて事前相談をしておくことの大切さを問うものです。その中でよく取り上げられるのが各種の「終末期に希望する医療」のアンケートに対する結果です。「何が何でも延命治療」を希望する人よりも「痛みの緩和だけはして欲しい」という人が圧倒的に多いのです。私自身も家族に対して文書で示していますが、やはり「痛みの緩和」です(この文書については、2020年9月1日付 「Ⅲ有限の人生そして『死』を意識して」の中で私の「尊厳死宣言書」を掲載しましたので参照ください)。

Ⅱ-126 実態調査結果について考える ④
医療の本丸とも言うべき病院に於いて、この最後とも言える希望に応えることが出来ていないのが現状。これはどう考えたらよいのでしょうか。その問いに即答できる力は私にはありませんが、私なりに考えてみたいと思います。
まず、痛みの緩和は、そのための薬剤や注射を処方するだけで解決できるものではありません。近年、痛みに対する薬剤などは飛躍的に発展しています。その中でどの薬剤をどの程度いつから投与するのかについて医師は高度な専門知識を求められ、その専門を研ぎ澄ませます。選択した処方の結果、十分な痛みの緩和に繋がらないこともあり、たえず患者さんの痛み(容体)とキャッチボウルをしながら治療方法を決定していきます。一方で痛みの緩和は狭い意味のガンに対する医療(治療)にプラスした医療となりがちです。言い方を変えますと+αの仕事になってしまうこともあるのではないかと思います。その場合病状が進んだ段階では生死に直結する治療に専念する傾向が強くなってしまうのではないでしょうか。
改めてガン患者さんへの医療は、ガンそのものへの治療と痛みの緩和を統合したものでなければなりません。したがってより以上に医師を中心としたスタッフの皆さんが患者さんに寄り添った医療が求められるのです。

Ⅱ-127 実態調査結果について考える ⑤
今から40年ほど前の1980(昭和55)年頃の医療現場では、「病気の治療は先生(医師)に一任」という時代で、ガンの「告知はしない」というのが一般的でした。その後病状と治療方針の説明が求められるようになり、次第に患者さん自身の自己決定が重要視されるようになりました。そして1990~2000年頃にかけてガンの告知時代へと変わってきたようです。しかし当時の病院内では告知する医師が増える中で、出来るだけ告知しない医師もいたのです。患者さんや家族の希望ではなく、ほとんどの患者さんに告知しないのです。その理由は意外と簡単なものです。告知をするということは、それ以降その患者さんに寄り添い、精神的サポートをしっかり続けなければなりません。ガンとその痛み、そして死への恐怖等々患者さんから多くの悩みを訴えられることになります。この訴えに応えられる精神的バックボーン、人間性そして専門性が問われることになるのです。したがってここに自信が持てない医師は、出来るだけ告知を避けようとしていたのです。
現在は、ごく一部を除いてガンの告知は当たり前のこととなりました。「緩和医療はガンの告知を受けた時から始まる」という考えも半ば常識になりました。しかし痛みの緩和については前述の通りまだまだが実態です。実態として病院で緩和医療が進まないのは、医療現場の人手不足、多忙、経営等々の問題等がありますが、医師を初めとするスタッフ一人一人が、痛みの緩和を含めた総合的医療についての実践を通して、患者さんに寄り添うことが必要なのではないでしょうか。
一方で「ガン」と診断された患者さんの10年後の生存率が、最新の調査で(国立がん研究センターなどの研究班、2020年11月19日発表)58.3%と発表され、10年生存率は改善傾向が続いています。このように治療法の進歩、治療現場の奮闘の結果としてこの改善数値になっています。したがって命の救いと同時に痛みの緩和を中心とする緩和医療の推進がますます求められるのではないでしょうか。


