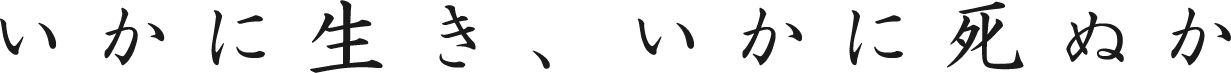
圓應寺 住職法話
住職法話 第149回
有限の人生そして死を意識して
【「いのち」の考察】164-168
「「自分史」について」
前回のこの項では、妻の入院、そして「寺はお庫裏(オクリ=住職の妻)さんでもつ」を実感したドタバタ劇について述べました。今回は、私自身の終活の一環としてまとめた「自分史」についてです。その冒頭と最後の内容を紹介します。
Ⅲ-164 三年かけて「自分史」を作成

私は今年の5月で満80歳の傘寿(本来は数え年で数えるのですが、最近は満年齢で数える場合の方が多くなってきたように思います)を迎えました。気持ちとしては「迎えることが出来ました」というのが実感です。70歳の頃からだったと思いますが、そろそろ自分史作成に取り組まないといけない年齢を感じていたのですが、気持ちはあっても実際にはなかなか出来ませんでした。ところが新型コロナ禍の中、比較的自分の時間がとれるようになったことから、思い切って「自分史~我が人生を振り返る~」と題して取り組みを始めたのでした。その結果約3年の格闘の末、A4サイズ、226頁の立派な(?)自分史ができあがり、妻と三人の子どもに渡すことが出来ました。終わった後は、成し遂げた充実・高揚感を期待したのですが、「終わった!おわった・・・」の後は放心、脱力感に襲われ、実に妙な想いとなってしまいました。どうしてそのようになってしまったのか自分でもよく分かりませんが、この感を脱するには二ヶ月ほどの時間が必要になったのでした。
以下、私の自分史の最初と最後の文章を掲載します(原文を一部補正)。
Ⅲ-165 冒頭の【自分史作成に当たって】より

今年・2020(令和2)年5月26日で、めでたくも(?)満年齢の喜寿を迎えた。埀石家血筋では、何年か前に最長命の年齢に達していたが、改めて喜寿を意識したことと今年の3月以降の新型コロナウイルス禍の中、時間ができたこともあって、かねがね頭の中にあった「そろそろ自分史を」の記述に取りかかることにした。
誕生日から一ヶ月遅れの6月25日に着手。どれほどの期間がかかるか全く分からないが、日々、ぼちぼちと取り組むことに。長い人生・・・?いや、今となっては短い人生とも・・。その私の人生。寺の子として生まれ、福祉専門の大学と就職を名古屋に求め、福祉は勿論のこと、ものの考え方を学ぶとともに、精神科医療福祉相談員として13年、様々な活動や学童保育などの地域活動。結婚して三人の子供にも恵まれた。大学時代を含め17年間の名古屋生活から、意を決して山形に帰郷。
山形県立中央病院医療福祉相談員と住職の二足のわらじ時代を25年。この間、寺では庫裏の建設に続き、本堂・位牌堂・客殿の建設、墓地移転工事そして墓地管理者確認と管理費請求に関する11年間に及ぶ裁判闘争。
定年退職後は住職一本として(真言宗智山派山形村山)教区長就任、東日本大震災慰霊法要などを主催。以後、「いかに生きいかに死ぬか」を主題に、講演、説法そして圓應寺ホームページを立上げ、自身の考えを表明してきた。
長くもあり、短くもある人生だが、振り返ってみると山あり谷あり、激動の人生でもあった。それを振り返り、まとめることが私自身の最後の大仕事と考え、筆を執ることにした。
この【自分史】が、子供たちと孫たちの人生訓の一助になることを願うものである。
Ⅲ-166 【終わりに当たって】より ①

「1」現在2023年1月に
この「自分史」を綴ることになったのは、新型コロナ感染症拡大による諸々の行事、旅行、宴会、お斎等々の自粛により、時間的余裕が十分に出来たことであった。勿論、それまでも自分の年齢を考え、そろそろ執筆を考えてはいたが、そのきっかけはやはりコロナであった。2020年6月に執筆を開始、現在(2023年1月)に至った。
「2」思えば、今の私は満79歳、5月に80歳に
歴代埀石家では最長の人生を送っている。60歳で定年を迎えた頃は、残りの人生を5年刻み、70歳からは3年そして75歳からは2年刻みで先の人生を考えて来た。そして幸いにもこの年齢に達したが、これだけ長生きできるとは若い時代にも退職してからも予想出来なかった。それは「埀石家は短命」との認識からであった。
これ程長生きできているのは、私自身、①体には神経質であること。②県立中央病院に長く在籍したことで、浅くも雑学的医学的知識(勿論、素人としてです)があったこと。③同じく、退職後も県中の関係医師との面識(これは人的財産)が有り、適格な医療を受けてきたこと等が挙げられる。
加えて、妻の房子も今日まで、それなりに元気に一緒に生活できて来たことは、人生を歩む上で、何よりの精神的支えであり生活の支えであった。二人とも支え合いながら生きていけることを願ってやまない。
Ⅲ-167 【終わりに当たって】より ②

「3」これから
あと何年の人生か不透明だが、人生の最終章にかかっていることだけは間違いないことである。長男夫婦、そして孫二人に埀石家と圓應寺を託すことになる。その引き渡しをできるだけ早く出来ることを願ってやまない。特に寺に関する事柄は複雑かつ山ほどある。私が老弱になってからは不可能であり、元気な間に託したいと強く願っている。
「4」圓應寺住職は埀石家が就いて私が三代目
初代・宥芳和尚(圓應寺住職通算15世)は東村山郡山辺町の貧しい分家に産まれ、山形市宮町一丁目の地蔵堂で生活し(長男の勝芳はここで生まれた)、努力を重ね武田神浄師の後を継いで圓應寺の住職となった。宥芳、勝芳が苦労を重ね、寺を守り発展させてきて、私が三代目の住職となって圓應寺に花が咲いた状態になった。
「5」心に留めておきたい住職という務めの本質
若い頃、少なくとも高校生の頃までの私は、将来寺の仕事に就くことに少々抵抗感があった。「寺(僧侶・住職)は、人の死をメシの糧にしている」といった風評を目耳にしていたからである。確かに寺の収入は葬儀、年回忌等の法要によっていることは事実である。こういった風評は長く私の頭に有り、なんとなくの後ろめいたものを持っていたのである。しかし、住職を務めていく中で、このような抵抗感や後ろめたさは一切無くなったのである。
寺(僧侶・住職)の第一の仕事は、亡くなった人々の霊を慰めると共に、喪主をはじめとする遺族や関係者のグリーフケア(身近な人との死別を経験し、悲嘆に暮れる人を、悲しみから立ち直れるように支援すること)に勤めることである。しかしそれだけに終わっては僧侶・住職としては失格である。人生には限りがある、必ずいつかはお迎えが来る。それを認識し、人として限りある人生をいかに生きるか、大切な日々をいかに生きるかを人々に問い、共に考えることがもう一つの大事な仕事である。
私の場合は、医療界に身を置いたことからその経験を基に問いかけが出来た。長男の場合は、教育、野球などを通してこの課題に取り組むことが出来るはずである。又、孫達も今後の人生経験を通してこの課題に取り組むことが必要である。
このように寺の役割を位置づけることによって、自分自身の生き方も明確になるのである。それは僧侶・住職として、そして何よりも人として大切なことなのである。
「6」圓應寺の歴史
当寺は延文元年(1356)、山形城主・斯波兼頼公が自身の兜に付けていた15センチ程の聖観世音菩薩像を城の守護仏として当地に奉安したことに始まった。長い歴史を持つとともに、最上三十三観音の札所でもある立派な寺院である。
この寺と埀石家の歴史を守り、支えそして発展させることを切に望んでやまない。
Ⅲ-168 【終わりに当たって】より ③

「7」【追】妻の入院と孫の新型コロナ陽性疑い
妻は2022(令和4)年1月8日夜、県中に救急入院。退院は18日で11日間の入院となった(【補正】このことについては、「急な妻の入院」と題して、①2022年10月1日付、②23年3月1日付で2回に亘って詳細に述べております)。
11日間の入院、この時期は新型コロナのため、面会が出来ず、医療者側への質問も説明も家族にはなし。幸い個室に入ったことでスマホによって一応の状況は把握できたものの、治療経過や先の見通しなどについては一切わからず、不安を抱えた毎日であった。
一方、この間は自分一人で何もかも。加えて葬儀まで入りてんやわんやであったが、近くに居る娘がよく買い物、留守番等々を担当して支えてくれたおかげで何とか乗り切ることが出来たものの、様々なことを考えさせられた11日間であった。その第一は自分の食事である。炊飯器の使い方については、どういうわけかつい最近その使い方を妻に聞いていたことで、初めてのことだったが何とか飯を炊くことが出来たものの、御霊膳(位牌堂の仏様に供えるお膳)に何を入れるか、洗濯機の使い方、銀行からの問い合わせ等々。これまで妻に一切をやってもらっていたことがわからないのである。
これで、「妻が先に逝き自分が残されるとしたらとんでもないことになる」ことを否が応でも実感させられたのであった。「男が残されると実に大変」といういつも聞く話を体験したのであった。そして妻の日常仕事の多さと大変さをも実感したのである。
これに加えて、孫のコロナ騒動が混乱に輪をかけた。1月15日(土)に、「孫のクラブ野球チームで感染者が出たということで、孫が明日PCR検査、月曜に結果が出る。出るまでは長男家族全員が、仕事と授業休み」との連絡。前日の金曜日に孫が寺に3時間ほど来ていたこともあり、場合によっては私自身も感染していることが危惧され、妻の入院と二重の鉛のような重しを抱えることになったのであった。
幸いにも、月曜に「陰性」の結果と妻の退院(翌火曜日)が決まり、両肩の鉛が落ちた感であった。今回の事態、特に妻の入院については、多くの教訓と道しるべを指し示すこととなった。よくよく自戒したいものである。
「8」最後に
長く私を支え、子供の成長の礎となると共に、遠く岐阜県の大垣から山形、それも寺という特殊な環境の中で、陰ながら最大限の力となった妻・「お母さん」を子供三人が中心となり、末永く最期までしっかり支えると共に、心からの面倒を見てくれることを願って筆を置くことにする。
この【自分史】が、子供たちと孫たちの人生訓の一助になることを願うものである。(巻頭「自分史作成に当たって」より)


