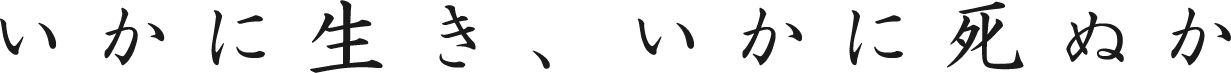
圓應寺 住職法話
住職法話 第59回
有限の人生そして死を意識して
【「いのち」の考察】57~62
「尊厳死について」
この項について3回にわたって「第二の人生」への切り替えについて、ご詠歌講の立ち上げ、早朝ウォーキング、ウォーキング特にスロージョキングについて述べ、習慣化の大切さについて考えました。
今回は、尊厳死について考えます。私たちは死亡率100%の中で今を生きており、いつかは必ず死を迎えることになりますが、問題はどのような状態で死を迎えることができるかです。近年、「尊厳死」、「自然死」、そして又「安楽死」等の死に方について語られるようになりました。今回からこれらの「死」について数回に亘って考えます。
Ⅲ-57.生と死を巡る現代の社会観

現代社会は、人間の永遠の願いである「少しでも長生きしたい」という一方で、高度な医療の下での「延命治療」等により、「なかなか死ねない時代」とも言われ ています。
本人は、元気な時から「自分が病気になって死期を迎えたら余分な延命措置をとらないでほしい!」と家族に表明していても、いざその時になると「少しでも長生きして欲しい」として、いわゆる延命治療を選択する例が沢山あるようです。「自分は延命措置なし」も家族にはいざその時になるとなかなか踏み切れなという相矛盾した実態があるのです。
このことは家族だけでなく、医療の現場にとっても悩ましいことなのです。患者さんの意志が文書等で明確に確認できる場合は「患者さんの意志に沿って‥」という形で家族と相談できますが、多くの場合は正常な意識下ではない目の前の患者さんの意志を正しく確認することは出来ません。したがって医療の現場では、延命治療を選択するか否かを家族と相談・協議することになります。ところが、家族間(親戚を含めて)でも考え方に相違があり、意見がすんなりまとまるわけではありません。
Ⅲ-58.外国の事例 ~米国女性 予告通り「安楽死」①~

2014年(平成26年)、末期ガン(脳腫瘍)で余命半年と宣告された米国のブリタニー・メイナードさん(女性 29歳)が、自らの意志で死を選択する旨をネットで公表しました。「尊厳死」「安楽死」「死ぬ権利」等々について米国はもとより、全世界でマスコミも取り上げ、その是非を巡って論議されました。勿論、日本でも大きく報道されましたので、記憶に残っておられる方も沢山おられると思います。
Ⅲ-59.外国の事例 ~米国女性 予告通り「安楽死」②~

メイナードさんはご自身が住んでいたカリフォルニア州から尊厳死法施行で「安楽死」が認められているオレゴン州に移住した上、2014年11月1日医師から処方された薬を飲み、家族に囲まれて予告通り自宅ベッドで自ら死を選択したのでした。
日本ではこの死を「尊厳死」ではなく、「安楽死」と位置付ける考え方が広く報道されましたが、同時に「尊厳死」「安楽死」そして「死ぬ権利」等々について議論されました。日本に於いても、安楽死を巡って医師の刑事事件化した経緯もあって盛んに論議される中、尊厳死についての法制化の具体的な動きもあります。
Ⅲ-60.日本に於ける「尊厳死(安楽死)」を巡る事件と裁判 ①

(智山伝法院講座を参考にまとめてみました)
日本に於いては、メイナード事例、つまり患者さんご自身の意志を尊重して医師が薬物を処方して死に至らしめた場合、その医師は殺人罪に問われることになります。この件に関した日本での事例2件を紹介します。
1、東海大学附属病院安楽死事件
患者さんは多発性骨髄腫のため入院していた1991年(平成3年)、「苦しむ姿を見ていられない」として長男は治療の中止を強く希望。これに対して担当の医師(助手)は、点滴等を外して治療を中止した。しかしその後も苦しそうな状態を見て、長男は「楽にしてやって下さい」と強く要請。要請に対して医師は塩化カリウム製剤(l塩化カリウムの血中濃度が上昇すると心停止を招き、米国では死刑執行時に使用されていると言われています。)を注射、患者さんは死亡しました。後日、この経緯が発覚して医師は殺人罪で起訴されたのです。
平成7年3月、横浜地方裁判所は被告人(医師)に懲役2年執行猶予2年の有罪判決を言い渡しまし、判決は確定しました。判決では、医師による積極的安楽死が許容されるための要件として次の4項目を挙げました。
- 患者に耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること
- 患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
- 患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くしほかに代替手段がないこと
- 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること
判決では患者の意思表示が確認できず、昏睡状態で痛みも感じていなかったことから上記1、4の要件に該当しないこと。一方で、患者の家族の強い要望があったことなどから、執行猶予が付いた判決となりました。
Ⅲ-61.日本に於ける「尊厳死(安楽死)」を巡る事件と裁判 ②

2 川崎協同病院事件
1998年(平成10年)58歳の男性患者さん。気管支喘息重積発作により低酸素性脳損傷で入院中も意識は回復せず。医師は家族に9割9分9厘脳死状態であると説明。家族は患者の気管内チューブを取り外すことに同意したとして、鼻から気管内に挿入されていたチューブを抜き取った。ところが、患者さんが苦しそうな呼吸を繰り返したため、医師は他の医師と相談、筋弛緩剤を看護師に静脈注射させ、患者さんを死亡させた事件です。
一審横浜地裁判決は、十分な検査がなされていないこと。患者さん本人の意志(家族を通しても)を確認していないことなどから殺人罪を適用、医師を懲役3年執行猶予5年としました。
2007年、東京高裁判決は、家族の要請で決断したものであったことを認め、「それを事後的に非難するのは酷な面もある」として、懲役1年6ヶ月執行猶予3年と刑を軽減しました。
2009年、最高裁は、「余命について的確な判断を下せる状況にはなかった。チューブを抜いた行為も被害者の推定的意思に基づくとは言えない」として、被告の上告を棄却し高裁判決が確定しました。 尊厳死などの延命治療の中止を巡って医師が殺人罪に問われたケースで、最高裁が判断を示した初めてのケースです。
Ⅲ-62.二つの事例で問題になったこと

患者さん自身が、自己決定として自らの死をどのように選ぶかという権利と医師の治療義務との一連の関係が論議されました。つまり患者さんの自己決定の尊重と治療義務との関係をどのように考えるかという問題です。患者さんの自己決定は、自身の病状が回復の見込みがなく死が目前に迫っていることを正確に理解し、その判断能力を持っていることが大切な前提条件となります。一方、医師(医療者側)には適切な検査・治療をし尽くし、治療が限界に達しているのか。又、複数の医師間で診断されたのか、患者さんには自己決定にいたる十分な情報と説明がされたのか。患者さんの意志が確認できない場合は、患者さんの考え方が推認できるのか、家族による推認は可能なのか。その場合の家族とはどの範囲か、その範囲の人であれば長年患者さんに会っていない人をも含めるのか‥‥等々。
我が国の現行法では、二つの事例のように医師は「殺人罪」に問われる状況下にあります。そのため「尊厳死」について法制化が検討されているのです。法制化の動きについては、この項の次回以降で述べます。


